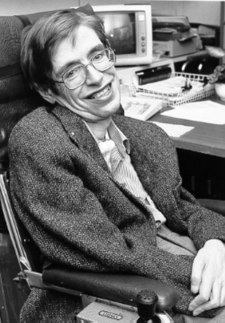先日今井書店に行ってみたら、WEEKLY BEST 1 に岩宮恵子さんの「好きなものにはワケがある」
NO.1![]()
になっていました!![]()
山崎豊子さんの最期の著作で話題の「約束の海」を抑えて、No.1![]() !
!
とても分かり易く書かれていますから、是非お読みください!
中高生に向けて、みなさんもそんなことありませんか?・・・のような文体で書かれていますが、大人が読んでも良いのですよ。
どれだけ分かり易く書くのか・・・が、書く人にとって最大の課題。
専門用語を並べたてた方が簡単なのですが、理解していただくためには、分かり易い言葉で、分かり易く書く・・・そういうことだと思います。
ぜひぜひ~~
さて、米子美術館横の「ハタノ」さんで、美味しいフルーツたっぷりのモーニングを食べ、米子図書館に行くのも、最近の楽しみ。。![]()
今井書店錦町店に行って本を見たり注文したりして、ラ・バールで美味しいカフェラテ飲みながら本を読むのと、ちょっと似たお楽しみ。。![]()
そして、米子図書館で、初めて本を借りてみました。
池田晶子さん
初めて知りました。
分かり易い言葉で哲学する・・・哲学エッセイ
そんなことをしていらっしゃいました。
1960年生まれの、私と同じ世代。
おお~
と思ったら。
2007年没
若くして亡くなられたんですね。
「私とは 何か さて死んだのは誰なのか」
「魂とは 何か さて死んだのは誰なのか」
「死とは 何か さて死んだのは誰なのか」
ご自身の生死をもって、哲学された方のようです。
「知るより 考えること」
読みました。
私と同じことで、怒ってる(笑)
非常に共感しました。
図書館に行かなければ分からなかったなぁ~
いい本、いい著者に出会えてよかった。
池田さんの魂とお話ししてみたいと思っています。
もちろん本を通じて。。
「14歳からの哲学」・・・考えるための教科書
「人生のほんとうのこと」
書店で注文してみました。
もう一つ借りたのは。
小林秀雄講演集のCD
もちろん以前から言っている、昭和の3賢人「3人の秀ちゃん」のお一人。
茂木さんも、岩宮さんも、池田さんも・・・
おそらく多くの知識人が、この方の語る言葉に共感しています。
茂木さんなど「親友だ!」
ぐらいの勢い・・・もちろんもう亡くなっていらっしゃいますから、魂の次元でのお話です。
4×2枚
計8枚のCD
もう繰り返し10回ぐらい聞いています。
今借りている中で、本居宣長について多く語っていますが、1730年生まれの本居宣長
ハイドンと同じくらいです。
方法論・・・つまりhow-toばかりやっていることの愚かしさを、もうこの時代から語っている。
これは本居宣長 言。
コンピューターは、細かくはなっているが、詳しくはなっていない、と、氏は語っています。
もう30年以上前に。
本当に怒っている。。
非常に共感。
「どうやったらいいんですか?」と、何も考えないで、how-toばかり聞くことの愚かしさ。
子供たちに伝えたい。
そして、やはり大人自身が、自分は大丈夫かと、自分の胸に手を当てて考えてみるべきだと思うのです。
もちろんまず自分自身。
自分は大丈夫と思うこと自体が、怖いことなんです。
ぁぁ・・・
もう、レッスンの準備しなくちゃ!
そそくさと、終わります。
お口直しに、スーラの絵葉書
ただ綺麗なだけじゃないんです。
でもこのお話は、またの機会に。。
ついでに佐野洋子さんも~
そうそう、小林秀雄の言葉の一つ。
「分かる」ということは「苦労する」と、同じ意味なんです。
非常に納得。
そういうことなんだなぁ~![]()
人生は意味深い~![]()





















































































 装丁は安野光雅さん
装丁は安野光雅さん
 この本の絵は熊田千佳慕さん
この本の絵は熊田千佳慕さん